
私はこれまで、現場の技術者として、何度も特許を出願してきた。
開発の中でアイディアを練り、弁理士と議論し、クレームを組み上げていく。
さらに日常的なSDI監視、量産前には、競合の特許調査もこなしてきた。
その経験を通して、はっきりと感じていることがある。
特許出願の経験は、技術者に“戦術スキル”を与える。
読む、避ける、攻める──この3つができて、はじめて「戦える技術者」になる。
申し遅れました。
本記事の案内人、磯賀場 真我(いそがば まわれ)と申します。
かつて「使えないエンジニア」と揶揄された時期もあった私だが、
転職と海外赴任を経て、5年間で約600万円の年収アップを実現。
「もっと早く知っていれば…」と思う仕事のコツや、評価されるポイント、
遠回りのようで確実な「急がば回れ」の仕事術、年収を上げるために本当に必要な考え方と行動を伝えている。
以下の記事もあわせて読むことで、この記事や本ブログの主旨への理解がより深まるはずだ。
▶️ このブログの全体像(年収アップメソッドの概要)
▶️ 年収推移の実例(5年間で年収600万円アップの軌跡)
① 読む:構造が見えるようになる

私は最初、特許を読むのが苦手だった。
請求項は独特の言い回しが多く、回りくどい。
何を主張しているのか、どこが重要なのか、さっぱり分からなかった。
初めて自分のアイディアが特許明細書として上がってきたときも、正直どう確認すればいいのかすら分からなかった。
もちろん発明者として内容を確認するのは当然だ。だが、新人の頃は「どこをどのように見ればいいのか」なんて、誰も教えてくれなかった。
教育があるわけでもなく、自分から聞きに行かなければ、「分かっているもの」として扱われてしまうのが実情だった。
そんな中で、実際に出願を重ねるようになり、
さらにはSDI監視や特許調査などに関わるようになって、
特許の読み方・書き方の “ルール”のようなもの が、次第に肌感覚で掴めてきた。
- 請求項と実施例の関係性
- 「おいて書き」による限定範囲の絞り込み方
- メイン/サブクレームの階層と意図
- 会社や弁理士によって現れる“書き方のクセ”
こうした要素が、まるでコードを解読するように読めるようになってくる。
こればかりはOJTで数をこなすしかない。
繰り返し触れる中で、特許は “文章” ではなく “構造” として見えてくるようになるのだ。
② 避ける:抵触判断の実戦感覚が身につく
量産前になると、他社の特許との抵触チェックが必要になる。
このとき、知財部と開発がどう役割分担するかは、企業によって違うかもしれない。
私の現場ではこうだった。
- 知財部の役割:検索式の設計、特許リストの抽出と一次ノイズ除去
- 開発の役割:内容の精査と抵触リスク判断(段階的に)
具体的には:
- 知財で除外できなかったノイズを開発側が除去
- 疑わしい特許を抽出
- 詳細確認によるハイリスク特許の絞り込み
- 最終的な抵触判断は、知財と共同で詰める
この繰り返しの中で、私は日本語特許であれば1〜2分で初期判断が可能になった。
ノイズ的な出願なら、瞬時に見切ることもできる。
このスキルは、そのまま「攻めの特許」を設計する力に直結する。
③ 攻める:広く、深く、回避されにくく

読む力、避ける力がついたとき、特許の書き方も変わる。
- 回避されにくい構成
- 広い権利範囲を確保できるクレーム設計
- 競合の動向を踏まえた “囲い込み” の意図
私は出願時、以下の点を強く意識していた:
- 抜け・漏れのない構成にする
- 他社が “逃げ道” を見つけにくいようにカバーする
- あえて抽象度を高めて(権利範囲を広くして)おき、用途展開やモジュール展開を想定しておく
特許は、単なる守りではない。技術で戦うための攻めの道具でもあるのだ。
補足エピソード:自分の特許と“再会”した日
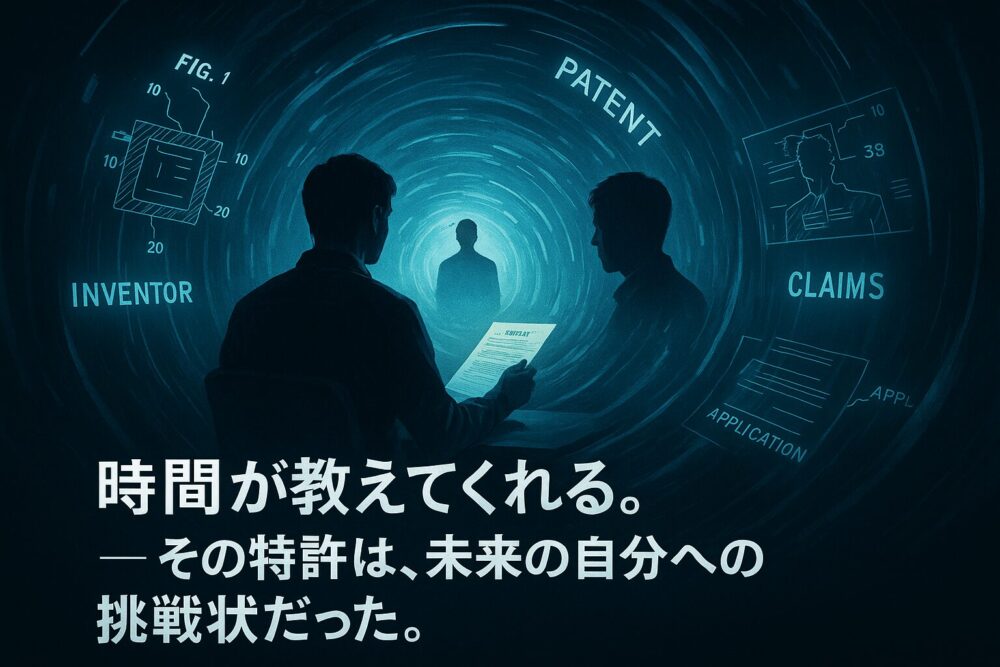
私自身、多数の特許を出願してきたが、それがきっかけでヘッドハンティングを受け、転職した経験がある。
当然、転職先は競合他社。
となれば──自分が過去に出願した特許の“回避”が必要になる局面が、ほぼ確実に訪れる。
こう聞くと、こう思う人もいるかもしれない。
「だったら転職を考えてるなら、特許なんて出さない方がいいのでは?」と。
実際、私の周囲にもそう考えて、転職後は一切自分で特許を書かないという同僚がいた。
(※なぜか、他人の特許にはしっかり共同発明者として名前を載せていたが…)
だが私は、断言する。
「転職を視野に入れているから」といって、出願をためらう必要は何ひとつない。
(もちろん、転職が完全に決まっているのであれば別だが。)
むしろ、今いる場所で全力を尽くし、自分の技術を磨き、
経験値を上げるチャンスとして、出願には積極的に向き合うべきだ。
未来は誰にも分からない。
だからこそ、転職後に自分の特許を回避しなければならないときが来たら、そのときに考えればいいのだ。
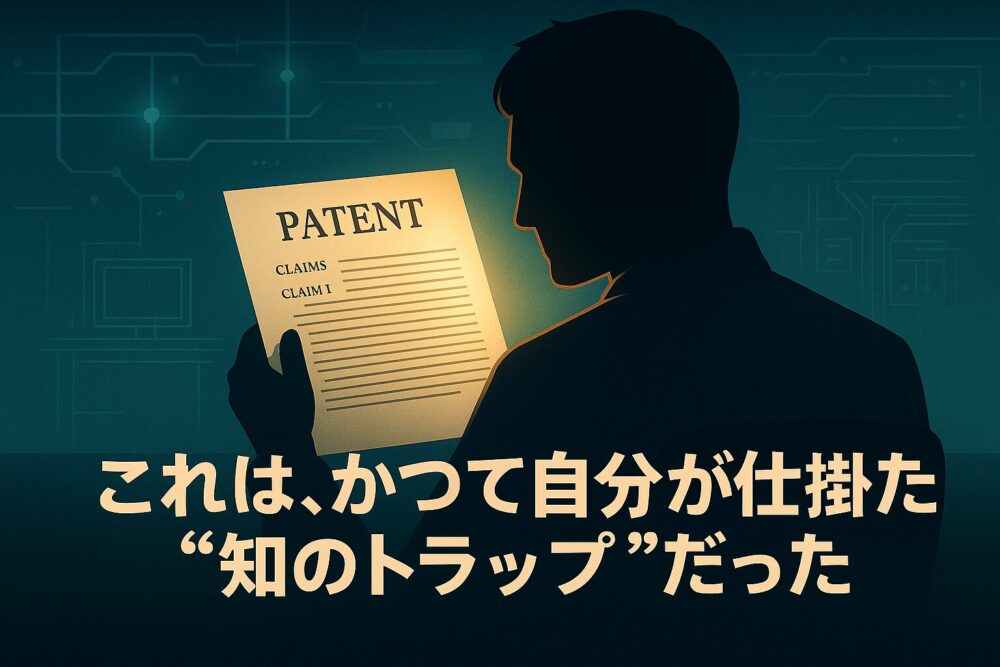
私自身、転職後に何度か自分の特許に向き合う場面があった。
「うわ、回避が面倒くさいな」「これ、出さなきゃよかったかも…」と頭を抱えたこともある。
だが、同時にこうも思った。
「ここまで厄介なのか。あのときの自分、よくやったな」と。
自分のクレームの出来の良さに、後から驚かされる。
あるいは、あまりの雑さに「昔の自分よ、ありがとう」と笑うこともある。
いずれにせよ、それは確かな成長の証であり、自分への勲章だと今は思っている。

結論:特許出願は、戦える技術者への“実戦訓練”──スキルは三位一体で進化する

特許出願は、単なる社内実績でも、ノルマでもない。
それは、「読める・避けられる・攻められる」スキルを実戦で鍛え上げる場である。
そして重要なのは、これら3つのスキルはそれぞれが独立しているようで、密接に結びついているということだ。
- 特許を“読める”ようになれば、他社特許の構成意図が見えてきて、“どう避けるか”が分かる
- “避ける技術”があれば、自分が出すべき特許の構成も、“どう回避されないようにするか”を逆算できる
- “攻めの特許”を出す経験を積めば、さらに“読む目”が鍛えられ、より深く特許の構造を理解できるようになる
読む → 避ける → 攻める → 読む
この好循環のサイクルを回せば回すほど、技術者としての視野も、実務力も、飛躍的に高まっていく。
特許出願は、そのきっかけであり、ステップアップの扉なのだ。
出願経験があるかどうか。
それは、“開発の深さ” と “視野の広さ” に、はっきりと差を生む。
📢 磯賀場 真我からひと言:
特許とは、知の格闘技である。
そして、出願経験とはその実戦稽古だ。
読む力、避ける力、攻める力──
それらをひとつずつ習得していくことで、技術者は本物になっていく。
健闘を祈る